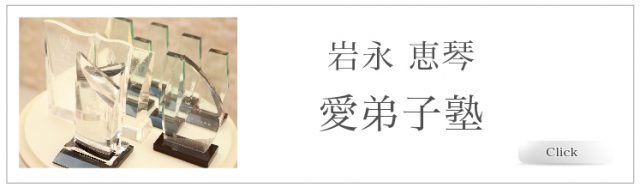「生プラセンタエキス」には活性が維持された栄養素が豊富に含まれています。それは肌細胞にとって貴重な成分であると同時に、雑菌にとっても栄養源となり、すぐに腐敗します。
インターネット上には当社以外にも「生プラセンタ商品」が見受けられますが、中にはまじめに開発しているとは思えない商品が散見されます。例えば次のようなケースです。
・スポイドボトルやドロップボトルなど外気が入り込む容器で、常温保管であるもの。
・製造方法が不明なもの。
・振ってもあまり泡立たないもの。泡立っても泡が1~2分で消えるもの。
・甘い香りが強く、プラセンタ本来のにおいがしないもの。
胎盤の細胞液をスポイドボトルなど外気が入り込む容器に入れて繰り返し使用することは到底考えられません。雑菌が外気と共に入り込み、すぐに腐敗してしまいます。相当量の防腐剤が入っているか、もともとプラセンタエキス自体があまり入っていないと考えられます。
技術を切磋琢磨するメーカーはむしろ大歓迎ですが、中には製造方法が不明なサイトもあります。「独自の方法」「長年の研究」「タンパク質をそのまま抽出」など抽象的な表現を繰り返し、とても長く分かりにくい広告になっています。こうしたメーカーの商品は、広告とは異なる製造方法になっている可能性があります。
非加熱の生プラセンタの中には、生卵のような本来の姿のタンパク質が含まれています。そのためボトルを振った時にとても細かく泡立ち、10分経っても消えることはありません。しかし加熱されたり、変質したタンパク質の場合は泡立ちが悪いか、泡立っても大きな泡しか発生せず、泡は1~2分で消えてしまいます。その場合はタンパク質の泡立ちではなく、防腐剤(界面活性剤)の泡立ちと判断できます。
胎盤の細胞液を100%抽出すると、においがどうしても残ります。これは当社にとっても長年の課題ですが、過剰な植物性精油は肌に良いものではないため、当社では使用していません。悪質な商品の中にはそれを逆手にとり「においが少ない」ことをPRし、甘く香ることがあります。
以上のようなケースは本来の「生プラセンタ」とは異なる商品である可能性があり、判断に迷う場合は当社へご連絡いただければ、調査させていただきますのでお気軽にご連絡ください。
当社へのご相談窓口: https://www.filtom.com/contact/
FILTOM